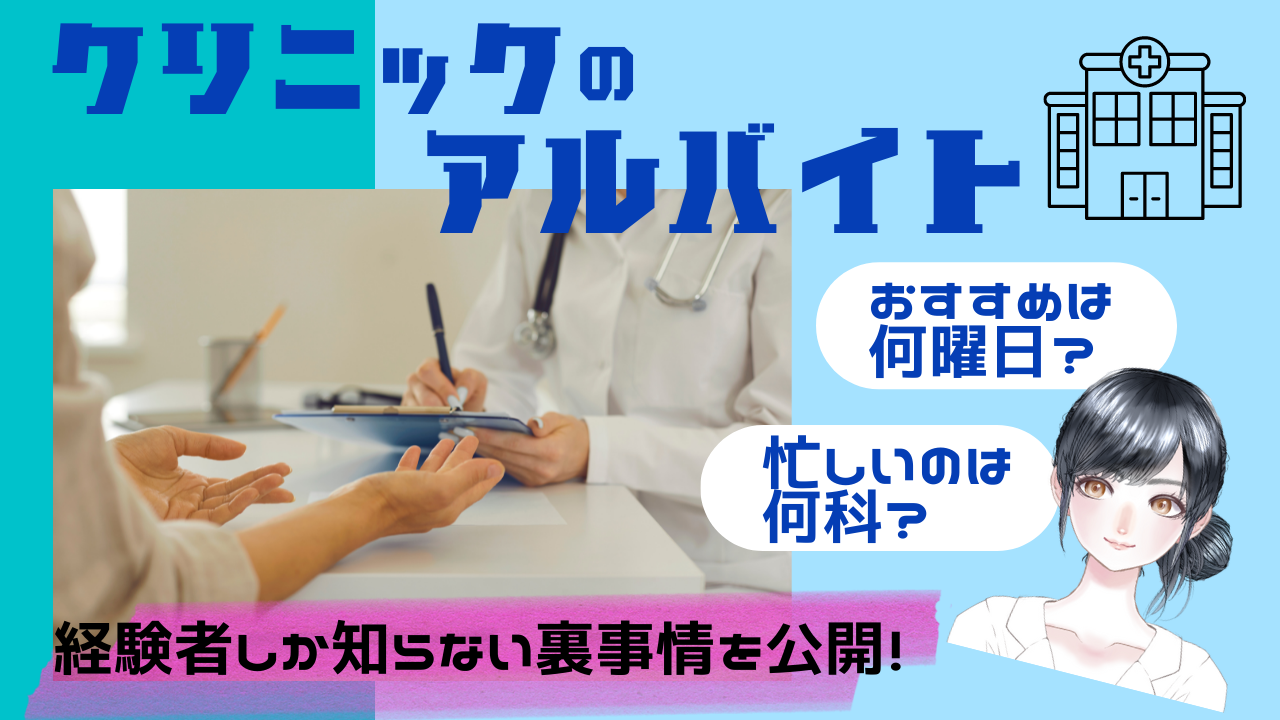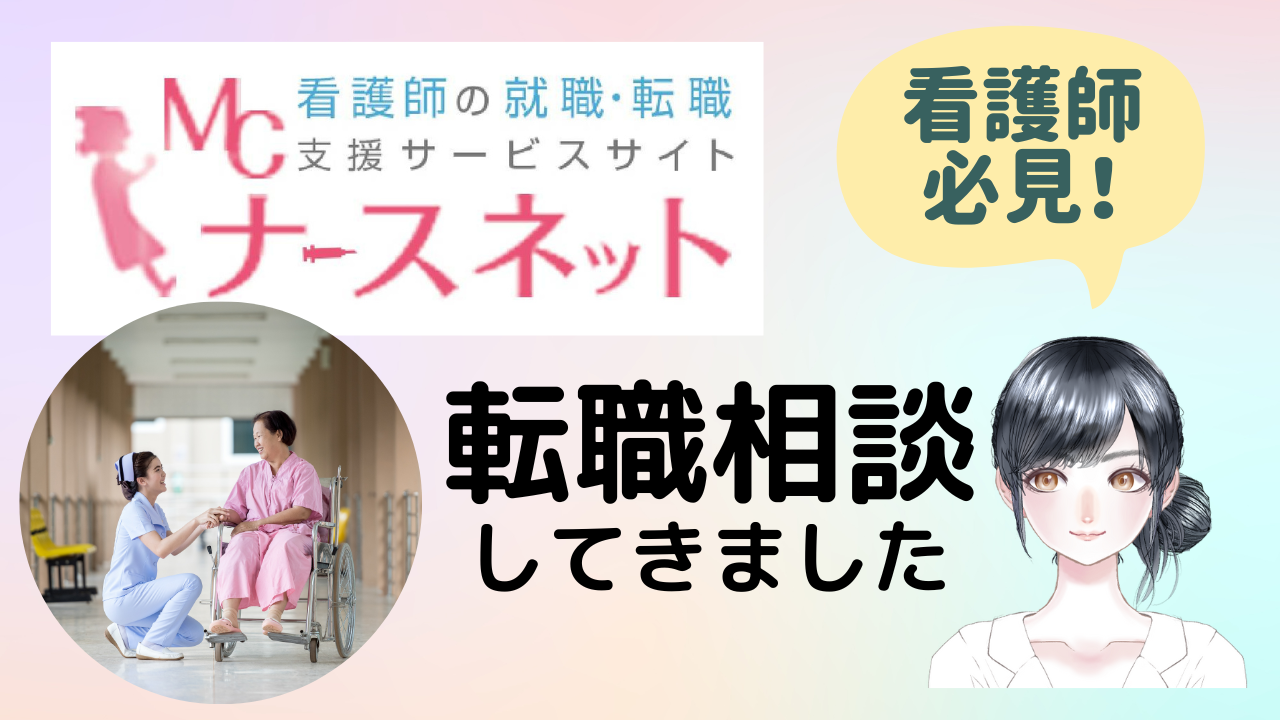看護師をしていると、アルバイトをする機会があるかもしれません。
大きな病院に勤めているとアルバイト禁止の場合が多いですが、非常勤やパートで勤めている場合、スケジュールの余裕があれば収入を増やすために単発のアルバイトをする場合があると思います。
また、転職の際、次の仕事を見つけるまでの間に派遣や単発スポットのアルバイトをする看護師も多いです。
この記事では、クリニックでの単発のアルバイトを経験したことのある私が、クリニックでの仕事内容や困ったこと、おすすめの日などを紹介していきます。
こんな人にオススメ
- 看護師のアルバイトを始めたい
- 新しいことに挑戦したい
- クリニックの仕事に興味がある
- 採血や点滴の技術を維持したい
本記事の内容
- クリニックの仕事内容
- アルバイトが困ること、戸惑うこと
- どんなクリニックが忙しい?
- 慣れるまではおすすめしない曜日
クリニックの看護師の仕事内容
クリニックの中で看護師が働く部署としては、診察室と処置室があり、規模によりますがそれぞれを1人ずつ以上の看護師が担当します。(診察室1人+処置室2人の3人体制など)
単発アルバイトの看護師は、基本的に処置室を担当することになると思います。
診察介助
診察室で、医師の診察に同席します。
患者さんに荷物を置いて椅子に座るよう声をかけたり、医師の説明に応じた介助を行います。
例えば、医師が「~~~を診ますね」と患者さんに説明していれば、ささっとそのために必要な機材・物品を用意したり、患者さんに適した体位(診察台に臥床or服を捲りあげる等)を調整してもらったりします。
カルテ記載
クリニックによりカルテの記載方法や記載内容はさまざまです。
特記事項がなければカルテを記載するのは医師だけのこともありますし、全患者さんのカルテを看護師が記載することもあります。
また、患者さんが看護師だけに話してくれた内容や、共有すべき情報なども記載します。
患者さんの案内
待合室から診察室へ来るよう声掛けをしたり、次は処置室へ、画像検査室(レントゲンやCT)へ等の案内をしたりします。
安定して歩行できない患者さんの場合、荷物を持ち歩行を付き添うこともあります。
処置室との連携
医師が患者さんへ説明しているのを聞き、処置室の看護師へ「採血入ります、点滴入ります」と患者さんが処置室へ来る前に先回りして情報を伝えます。
点滴のオーダーは、カルテから注射箋を印刷し、処置室のスタッフへ手渡すことが多いです。
採血(検査装置の操作も含む)
採血は、処置室で行います。
医師の指示に従い必要な検査項目がだせるスピッツを用意します。
クリニックでの採血は、①クリニック内ですぐに結果を確認し、患者さんへ説明するものと、②外注(院内で測定できない項目を外部に注文委託する検査)があります。
すぐに結果が必要な採血は、処置室で検体を採取後、看護師が遠心分離機や血液検査装置を操作し、結果を出します。
静脈内注射
注射のオーダーは、静脈内注射がほとんどです。
クリニックは入院病床がないため、その場で注射を打ち、抜針し、帰宅してもらうため、点滴ボトルをぶら下げルートを満たし滴下調整し・・・というオーダーは少ないです。
複数の注射でも、翼状針を使い順々に投与し、その場で抜針します。
1時間の点滴でも翼状針
患者さんの状態によっては、500ml以下くらいの点滴がオーダーされることもあります。
しかし入院することはないため、30分から長くても1時間程度で点滴は終了することが多いです。
留置針を使用せず、翼状針で正中静脈からの投与がほとんどです。
都度台や椅子の消毒
患者さんが処置室の椅子や採血台、ソファーや処置台(ベッド)を使用する度に、消毒を行います。
カルテを回す
電子カルテを導入しているクリニックでも、問診票やオーダー用紙(採血・注射・画像検査など)、来院時に測定した血圧のメモ等を合わせて、ファイルに入れ各担当者へ回します。
例えば、このような流れです。
来院後受付で問診票と血圧の用紙をファイルへ入れる
↓↓↓
診察室でオーダー用紙を追加する
↓↓↓
処置室でオーダー用紙を確認し、必要な採血や注射を実施し、実施済みチェックを打つ
↓↓↓
画像検査室でオーダー内容を確認し、技師さんが検査を実施し、実施済みチェックを打つ
↓↓↓
受付にカルテを戻す
※採血結果や画像検査の結果は電子カルテで確認するため、全検査が終了したらカルテは受付の事務スタッフへ戻します。
どの部署もクリニック内の短い距離なので、ファイルを看護師が次の担当者へ手渡すために運びます。
翌日の準備
翌日の予約状況を確認し、事前に準備できる物品があれば、準備しておきます。
薬剤の在庫管理
大きな病院であれば処方した点滴が自動的に発注されるところもありますが、クリニックはほとんどが在庫数(残数)に応じての発注となります。
生理食塩液などは患者さん毎に1つ開封するのではなく、100mlなど大きなボトルから患者さんの注射オーダーに応じて必要な量だけ抜き取る形で1日かけて使用することもあるため、実際の残数に合わせて発注が必要となります。
清掃
規模にもよりますが、クリニック内には清掃専門のスタッフはいないことが多く、看護師や検査技師、受付の事務スタッフなど、手の空いた人がごみを集めたり、清掃を行ったりします。
どんな患者さんが多い?
年齢層は広い
クリニックの診療科にもよりますが、その地域に住む子どもからお年寄りまで、患者さんの年齢層は幅広いです。
ADLは軽介助まで
自宅で過ごせる人がクリニックへ通院するため、病院や施設より患者さんのADLは高いです。
クリニックには入院施設はないため、自宅で大きな変化があり動けなくなった患者さんは直接入院可能な大きい病院へ受診することが多く、クリニックでADL介助をすることは基本的にはありません。
定期治療
「1か月に1回注射を打つ」など、定期的に行う治療があり予約受診する患者さんが多いです。
症状チェック
2~3か月毎に定期的に通院し、症状の変化がないか観察したり、継続して内服薬を処方してもらったりする患者さんも多いです。
症状悪化の飛び込み
元々定期的に治療をしたり内服薬を処方してもらったりして様子を見ていた患者さんが、急に症状が悪くなったため、予約日より前倒しで受診することもあります。
発作が出た時などがあります。
初診
一度もそのクリニックに来たことがない患者さんも、クリニックの看板を見たりホームページを見たりして、その診療科に関連する症状があるため、初めて受診する場合があります。
救急搬送
交通事故や急な発作・症状の悪化などで救急車を利用した人が、救急隊の判断でクリニックへ搬送されることもあります。
実際に働いて困ったこと、戸惑ったこと
採血関連
初めて見る駆血帯
駆血帯にはいくつか種類があります。
- ゴムチューブの先に金属のクリップが付いたもの
- ゴムチューブのみ
- ゴムチューブが平たいテープのような形のもの
- ワンハンドで使えるベルトタイプのもの
などなど。見たこと聞いたことはあるけど、使ったことがないものもありませんか?
それぞれの病院やクリニックに置いてある駆血帯はこれらのうち1~2種類程度だと思います。
「採血お願いします!」と言われて、いきなり駆血帯の使い方がわからなくて困ってしまうこともあります。
クリニックでのアルバイトの際は、My駆血帯があれば持参すると安心です!
採血は検査結果を自分で出す
個人的には、これが1番驚きました。
クリニックの規模にもよりますが、血液検査の検査装置を看護師が取り扱うクリニックも多いです。
これまでの職場が大きな病院だった場合、採血した検体を「お願いしまーす」と届ければ技師さんが対応してくれるため、待っていれば検査結果が出ます。
外注の採血は同様ですが、クリニック内ですぐに検査結果を出して方針を決定する場合、手際よく検査装置を操作しなければなりません。
クリニックによって検査装置の種類が異なるため、一度覚えても働く場所が変われば操作方法は再度覚える必要があります。
私がよくアルバイトに行ったクリニックでは、
①まず遠心分離をするための機械に検体を設置します。
②遠心分離中に、検査項目を確認し、それぞれの項目を検査できる「チップ」を1枚ずつ用意し正しい向きに重ねます。
③検査装置に患者情報を登録し、検査項目に応じたチップをセットし、重りを乗せます。
④遠心分離できた検体を検査装置にセッティングし、検査を開始します。
⑤検査項目を確認し、HbA1Cがあれば遠心分離にかけていない血液で専用の検査キットと機械を使用し検査します。その際もキットのバーコードを読み取り患者情報を登録し、電子カルテと連携させます。
「とりあえず出す」ができない
クリニック内で結果を出す採血も大変ですが、外注の採血もまたプレッシャーがあります。
入院患者さんの採血なら、ほとんどは病院内の検査部で完結するため、「この患者さんの採血はどうしても難しい、規定の量より少ない血液量しか採れなかったけど、これで検査できないかとりあえず提出してみよう」「採血に時間がかかってしまったから、血液が凝固していないか心配だけど、とりあえず提出してみよう」ということもできたと思います。
しかし、クリニックでの採血の場合、患者さんは帰宅し次回受診時に結果説明を受けるため、うまく結果が出なかったと言って再度採血させてもらうことはできません。
必ず検査結果を出せる検体を採らなければならないのです。
独自ルール
検査装置にトラブルが起こり結果がきちんと出せなかった場合や、検査項目を追加する場合など、「もしかしたら必要になるかもしれない」と少し多めに血液を採取して保管しておいたり、結果の出たスピッツも念のため保管しておいたりと、そのクリニック独自の採血に関するルールがある場合もあります。
半日の診療が問題なく終わったら、念のため保管していた血液・検体をまとめて破棄しますが、初めはそれを知らずに都度破棄していました。
点滴関連
点滴は注射箋の参照のみで認証なし
点滴を準備する際、診察室を担当する看護師が印刷した注射箋を参照して混注します。
投与時も同じ紙を用いて、患者さんのフルネームを名乗ってもらい、投与します。
病院であるような薬剤に貼付する患者名や薬剤名の載ったラベルはありませんし、バーコード認証などもありません。
同時に2人以上の点滴を準備する際には、混注したものがどれがどの薬剤かわからなくならないよう注意が必要です!
よく使う点滴を作り置きすることがある
「この注射は毎日10人以上オーダーされるから、とりあえず5セットくらい作っておいて」と初めて言われたときは、衝撃でした。
確かに複数のアンプルをカットしたり生食の量を測ったりと手間のかかる注射ではありましたが、まだオーダーもされていない、投与する患者さんも決まっていない点滴を作り置きするなんて、病院ではあり得ないですよね。
規格の違いがほとんどない
上記のように作り置きできる理由として、同じ薬剤の規格違い(容量違い)がほとんどないというのもあると思います。
クリニック内で使用する薬剤の種類は限られており、在庫のある薬剤しかオーダーされないため、同じ症状なら使用する薬剤は同じであることがほとんどです。
ダブルチェックできないときも多々
診察室も忙しい場合、処置室で点滴を準備する際に注射箋と薬剤を看護師2名でダブルチェックできないときも多々あります。
オーダーを確認して自分で薬剤を棚から取り出し、混注して投与する、という一連の流れを自分1人だけでやるということに初めは戸惑いました。
大きな病院であれば、医師のオーダーを薬剤師が2名で確認して薬剤を払い出し、受け取った看護師も2名で確認して混注し、認証した上で投与することと思います。
あまりにも他の人の目を介さずに患者さんへ投与するため、怖くて何度も6Rを確認しました。
生食はボトルから使っていく
薬剤のコストの問題で、生食20mlを複数使用するより生食100mlから5回分使用することがあります。
アンプル製剤のような清潔な保管ができないものはそのようなことはしませんが、ゴム栓のある薬剤でその日のうちに使用できるものはコスト優先で対応することもあります。
滴下速度の指示なし
注射箋には、患者名・薬剤名・規格・個数が記入してあり、ボトルを吊り下げて投与するタイプの点滴でも同様のため、投与速度がわかりません。
しかしクリニックの性質上診療時間内には帰宅してもらう必要があるため、何時間もかけて点滴することはなく、薬剤の特徴や患者さんの状態・既往などから判断して15分~1時間程度で安全に投与します。
翼状針の固定
病棟に入院している患者さんの点滴は、24時間持続であったり、1日に複数回であったり、連日使用したりということが多いため、サーフロー(留置針)を使用することが多いと思います。
しかし、クリニックで留置針を使用することは基本的にはなく、1時間程度の点滴でも採血と同様正中静脈を選択し、翼状針で投与します。
翼状針の固定方法は学生時代や新人看護師時代に習いましたが、ほとんど実践したことがなかったため、新鮮でした。
その他
物品に適応できない
先に記載した駆血帯の件もそうですが、「血圧を測ってください」「心電図をとってください」など、これまでの経験から当たり前に実施できる内容を依頼されたときも、クリニックにある物品の使い方がわからずスムーズに実施できないことがあります。
5年以上看護師をやっているのに「この血圧計、どうやって使うんですか?」と教えてもらったことがあります。
患者さんの名前が記憶から消える
これまで病棟で働いていた時は、「000号室の○○さんにこれをして、111号室の△△さんにこれをして・・・。あ、××さんの□□ですね?すぐ対応します!」など、複数の患者さんの名前や顔と、病名・治療内容などを把握して仕事していたと思います。
しかし、初めてのクリニックで次々に来る初対面の患者さんの対応をしていると、採血や点滴の際にフルネームで名前を確認しているにも関わらず、医師や別の看護師から「☆☆さんの採血ってもう終わった?注射の内容変更したいけど間に合う?」など聞かれても、誰が誰だか、終わったか終わってないかも訳わからなくなってしまうのです。
新人の頃の気持ちを思い出す・・・
部署ごとにカルテを運ぶ
病院の外来受診をイメージすると、その日に必要な書類(受付票や検査の予約票など)は、患者さんが自身で次の部署へ運び、その部署の窓口へ提出してくれることが多いです。
例えば、病院入口で来院受付をして、採血センター→放射線センター→外来診察室と順に患者さんが予約票を持って回ってくれます。
しかしクリニックでは、患者さんが運ぶのではなく、スタッフ間での直接のやりとりが多いです。
確かに、自分がクリニックを受診する際も、いつも会計は受付スタッフに呼ばれ、自分で書類を提出することはなく手ぶらで窓口へ行っていました。
独自ルールが多い(止血バンドとか)
複数のクリニックで働いたことがある人でも、クリニックごとの「独自ルール」のようなものにはなかなか初めは適応が難しいと思います。
私がアルバイトで行ったクリニックでは、採血や静脈注射を実施したら抗凝固剤の内服の有無や自分で押さえることができるかどうかに関わらず、全員止血バンドを使用するルールでした。
また、止血バンドを外し忘れることがないよう、問診票やオーダー票などの入ったファイルに「止血バンド使用中」という紙を追加で入れ、その紙が入っていたら次の部署(画像検査室や受付など)のスタッフが止血できていることを確認して止血バンドを回収する、というものでした。
時間はぎりぎりにスタート
病棟看護師をしていると、勤務開始時間ぎりぎりに出勤する人はほとんどいなかったと思います。
ママさんで、お子さんの保育園へ送ってから出勤する人はあまり早くは出勤できませんが、未婚の看護師は勤務開始時刻の30~1時間前に出勤して情報収集したり、点滴を用意したりと、いわゆる「前残業」を当たり前のようにしています。
しかし、クリニックは勤務開始時間ちょうどに出勤すれば問題なくて、さらに医師は診療開始時刻に少し遅れて出勤する人も珍しくはないです。
クリニックのコミュニティ
これは個人的な感想で、どこのクリニックでも共通する話ではないと思います。
病棟だと看護師の人間関係の悩みは多いと思います。
それに比べクリニックの人間関係はあっさりしているのかな?というイメージでした。
しかし、午前診療と午後診療の間に一度解散し自宅へ戻る場合はスタッフ同士でいろいろ会話する機会が少ないですが、昼食をスタッフで一緒に外食したり、1つの休憩室で過ごすような場合は、「やっぱり看護師の人間関係だな~」と実感してしまいます。
話題が、「○○さんはこの前失敗して院長先生に怒鳴られていた」「△△さんと□□さんは仲が悪いから気を遣う」「××さんはもう3か月経つのに仕事の覚えが悪い」などなど。
その場にいない人のネガティブな話題が止まりません。
1対1で話すとみなさん優しくて良い印象なのですが・・・
忙しいクリニック
皮膚科は夏、循環器・小児は冬
医療者は経験から想像できると思いますが、クリニックには忙しい季節、落ち着いている季節があります。
冬は感染症が流行したり、寒さで血管が細くなったりすることで、さまざまな病気が多くなる傾向です。
しかし、皮膚科は夏の方が汗をかいたり日に焼けたりすることで、トラブルが増えます。
クリニックでの仕事が初めての方は、いきなり忙しい時期に行くと苦労するかもしれません。
例えば、予防接種シーズンは他の時期と比較し格段に忙しいです。
まずは、そのクリニックの診療科の「落ち着いている季節」であるかに注目して選ぶことをおすすめします。
メディアの威力
芸能人が病気になるとニュースになることが多く、それにより一気にその病気の知名度があがります。
また、芸能人が「○○の治療が良かった!すっかり治った!」と発言すると、その治療をできるクリニックが急に人気になることがあります。
例えば、北斗晶さんの乳がん治療がニュースになっていた時期は、乳腺クリニックには「北斗晶さんのニュースを見て、心配になったので来ました」という人がかなり多かったです。
また、オードリーの若林さんが片頭痛の新しい治療薬を使って症状が改善したことが話題になったため、現在も片頭痛治療を希望する患者さんは多いです。
外傷が来ると処置もある
整形外科や脳神経外科・内科などは、交通外傷の精査のため受診する場合があります。
骨折や脳内血腫の評価が主な目的であっても、怪我をして出血していれば傷口を洗って処置をしたり、必要に応じて縫ったりする場合があります。
予約を取って受診する患者さんで処置があることはあまりありませんが、予約なしの飛び込みで来る患者さんの場合は急遽処置をすることがあります。
救急搬送があると忙しい
救急車というと、大きな病院に搬送するイメージがあるかもしれませんが、患者さんの病状次第ではクリニックで対応することも多いです。
大病院を受診しなくても大丈夫とは言っても重症なので、待合の順番を変更したり、滅多に使わない機材や薬を使ったりと、忙しくなります。
クリニックで診察した結果、やっぱり大きな病院に移る方が良いとなる場合もあり、その際には書類の準備や説明などの調整も必要となります。
忙しいと言っても病棟とは感覚が違う
「病棟勤務は忙しいから、クリニックでゆっくり働きたい」と考える看護師は多いと思いますが、クリニックも忙しい時は忙しいです。
気づけば待合室がいっぱいになっていたり、処置室の前に行列ができていたりします。
採血結果を見て医師が指示をだす場合には早く採って検査装置をまわさないといけないですし、痛み止めや吐き気止めの注射を待っている人には早く対応しないと申し訳ないです。
そこに急患が来るとなれば、もうてんやわんやです。
私は「今日は、滅多にないくらいの忙しさだよ」と言われた日も働いたことがありますが、病棟での「忙しい」とクリニックでの「忙しい」は少しニュアンスが違うと思いました。
クリニックでの「忙しい」は、=「患者さんを待たせている」で、
病棟での「忙しい」は、=待たせている状況は当たり前で、「3時間残業しても到底終わらないであろう仕事量が積み残されている」
ような状況だと思います。
その違いは、デスクワークの量の違いや、対応するイベントの規模や数の違いが大きいと思います。
病棟看護師は入院が1件あると、カルテ作業が大量にありますし、安定している患者さんでも1人ずつに長文の看護記録や入力事項があります。
また、翌日の準備として、手術予定の患者さんがいればチェックリストを作成したり、処置の予定があれば必要な物品を確認して揃えたりといったこともあります。
忙しい曜日
月始めの土曜日は、最も忙しい
クリニックの忙しさは季節によって変わるという内容も書きましたが、曜日によっても変わります。
曜日による忙しさの波は、診療科に関わらずほとんど共通していると思います。
忙しい曜日順に並べると、
土→金→月→火→水 です。(木曜日が休診の場合)
最も忙しいのは土曜日で、理由としては平日に受診できない患者さんが来るためです。
また、翌日が日曜日で、週末はなかなかどの医療機関も受診が難しいため、受診するかどうか迷っていた人が「念のため行こう」と判断するのが土曜日になることが多いです。
次に忙しいのは金曜日です。
木曜日が休診日のクリニックが多く、「本当は木曜日に受診したかったけど休みだったので我慢していた」という人がいるため、忙しくなりやすいです。
また、土曜日と同じで「週末になる前に」と考える人も多いです。
その次に忙しいのは月曜日です。
週末に体調が悪くなっていた人が、クリニックの営業する週明け月曜日まで待って受診することが多いためです。
また、同じ曜日であっても月始めの方が混みやすく、忙しいです。
その理由についてははっきりと明言できませんが、おそらく①給料日の後だから ②高額療養費制度は月をまたぐと損になるから といったところだと思います。
クリニックのアルバイトをするなら
クリニックのアルバイトをするなら、慣れるまでは土曜日は避ける方が安心です。
先述の通り土曜日は忙しいことが多いですし、ベテランの看護師が家庭の事情で休みをとっていることも多いためです。
不慣れで忙しい日を担当し、しかもベテラン看護師がいないとなると、なかなかハードです。
ベテラン看護師は先生とのコミュニケーションも上手いので、先生の機嫌も良いです!
初めてのクリニックのアルバイトは、暇な時間もある曜日を選ぶことで、そのクリニックのよく診る病気やよく使う薬剤、独自ルールを教えてもらったり、使ったことのない機械の操作方法を教えてもらったりできます。
まとめ
クリニックで働く看護師について、イメージで来たでしょうか?
どの職場でも、慣れるまではわからないことが多く苦労します。
その中でも、比較的落ち着いていると予測される曜日や時期を知っていれば、ゆっくり教えてもらえるので覚えが早いです。
また、クリニックは病棟と比べて暇だろうと思っている人は、案外忙しくて驚くかもしれません。
しかし、来ている患者さんに関する仕事が終われば終わるので、残業の量としては病棟より格段に少ないと思います。
ただ注意すべきは、院長先生の方針によっては「救急車は断らない」「多少診療時間を過ぎても受け入れる」という場合もあるため、そのような方針の先生だと、残業は珍しくありません。
クリニックでの仕事のポイントは、とにかく同じクリニックに行って慣れるということです。
何度も同じクリニックで働いていれば使う薬剤の種類やよく来る患者さん(疾患)もわかるようになりますし、物品の使い方がわからない、クリニックの暗黙のルールを知らなかった、という状況は防げます。
クリニックでの単発バイトをするなら
私はここに登録してクリニックのお仕事を紹介してもらいました!