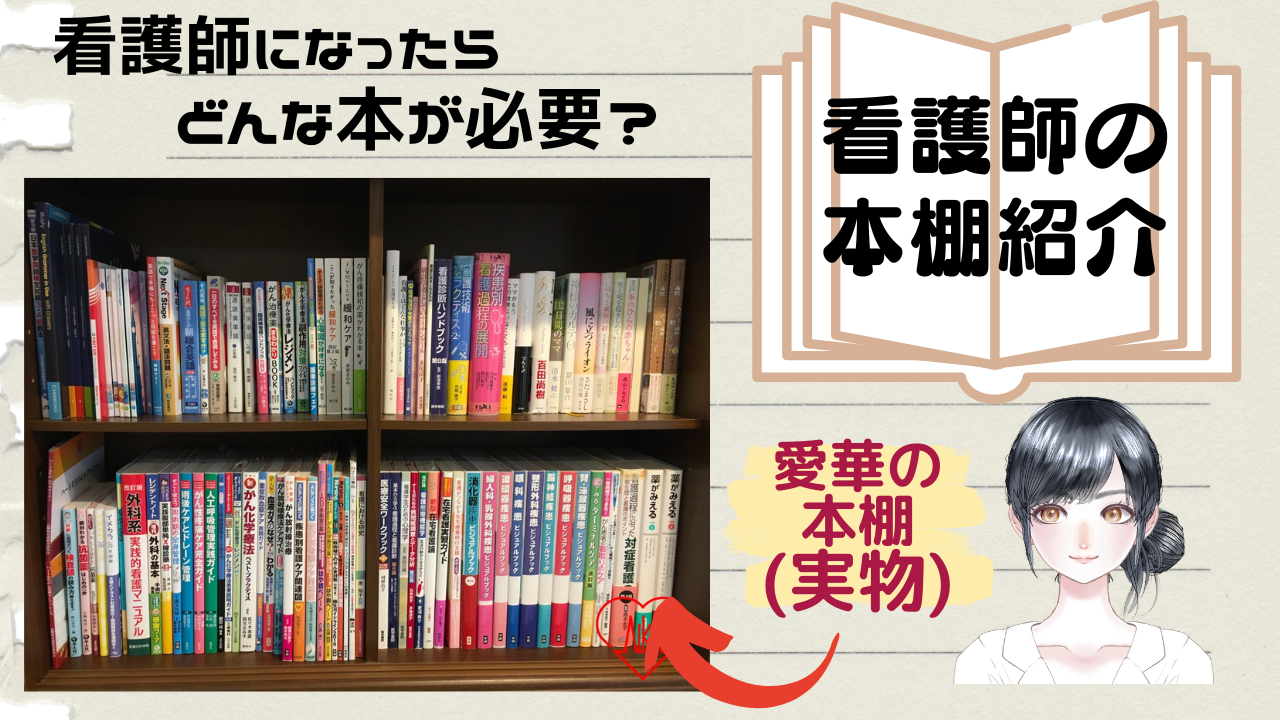看護師は毎日薬を取り扱いますが、その薬についてきちんと理解できているでしょうか?
患者さんから「それは何の薬?」「どうして前の薬から変更になったの?」「副作用は大丈夫かしら?」など、質問を受けて焦ったことがある看護師は多いと思います。
自分で投与する薬について正しく理解することは、患者さんの安全・安心に繋がります。
今回は、私が薬剤関連の勉強に使った本を紹介します。

絶対わかる抗菌薬はじめの一歩
黒・グレー・青・水色で印刷されています。
この本は感染症ごとではなく、抗菌薬の種類ごとにまとめられており、それぞれに演習問題が載っています。
ケーススタディも5例あり、実際の抗菌薬使用をイメージできます。
- Lecture 1:スッキリわかる感染症へのアプローチ
- Lecture 2:これが必須の知識~各抗菌薬の特徴と使い方~
- いざ実践!CaseStudy
問題がたくさん載っており、判断は難しくても読んでいるだけで楽しいです
ねころんで読める抗菌薬
かわいい4コマ漫画や面白い例えが多く、Pointは大きな文字で目立たせてあります。
この本は抗菌薬ごとのまとめではなく、感染症ごとに「どの抗菌薬を何日間使用する」というのが書かれています。
実際の抗菌薬の使用はこの本の通りとは限りませんが、飲みきりで終了なのか、先生が処方し忘れているのかを考えるときの参考になります。
- 第1章:感染症をみるための5つの心得
- 第2章:よくみる感染症でわかる抗菌薬処方のポイント
- 付録:各系統の抗菌薬
本当に寝転んで読めるような、ストレスなくどんどん読みたくなる本です。
薬がみえる Vol.1、Vol.2
医療従事者や医療系の学生で知らない人はいないと言っても過言ではない大人気シリーズ「病気がみえる」の薬バージョンです。
全編カラー印刷で、タイトルの通り視覚的に捉えられるよう図が多く使われています。
例えば、一言で「血圧を下げる薬」と言っても、作用機序はさまざまであり、患者さんの状態によって「この作用の薬は中止するほうがいい」「この作用の薬なら関係なく内服を続けた方がいい」など指示が異なる場合があります。
指示をするのは医師ですが、「続けて大丈夫かな?」と疑問を持ち、医師へ相談するのは看護師の知識が必要となります。
薬がみえるはVol.4まであります。
Vol.1
- 神経系の構造と機能
- 自律神経系に作用する薬
- 体性神経系・筋の疾患と薬
- 中枢神経系の疾患と薬
- 循環器系の疾患と薬
- 腎・泌尿器系の疾患と薬
Vol.2
- 糖・脂質代謝の疾患と薬
- 骨・関節・カルシウム代謝の疾患と薬
- 内分泌系の疾患と薬
- 産婦人科系の疾患と薬
- 血液系の疾患と薬
- 免疫・炎症・アレルギー系の疾患と薬
- 眼の疾患と薬
- 耳鼻咽喉の疾患と薬
- 皮膚の疾患と薬
Vol.3
- 消化器系の疾患と薬
- 呼吸器系の疾患と薬
- 感染症と薬
- 悪性腫瘍と薬
Vol.4
- 薬力学
- 薬物動態学
- 相互作用
- 製剤学
- 薬事の使用と実務
自分の診療科の範囲だけでも持っておくと便利だと思います。
ICU・手術室の薬 はや調べノート
手術中や手術後に使用する薬剤に特化して書かれている本です。
- 第1章は中枢神経系用薬
- 第2章は末梢神経系用薬
- 第3章は強心薬
- 第4章は不整脈用薬
- 第5章は血圧降下薬
- 第6章は血管拡張薬
- 第7章は利尿薬
- 第8章は循環器官用薬
- 第9章は気管支拡張薬
- 第10章は解毒薬・中毒治療薬
- 第11章は消化性潰瘍治療薬
- 第12章はホルモン製剤
- 第13章は滋養強壮薬
- 第14章は血液・体液用薬
- 第15章は代謝性医薬品
- 第16章は生物学的製剤
- 第17章は抗菌薬
- 第18章は抗真菌薬
- 第19章は抗ウイルス薬
術中・術後は患者さんの状態変化が急に起こることも多く、1分1秒を争う環境下で薬剤を使用するため、薬剤についての知識は必須です。
何のための薬?適正な量は?副作用は?頭に入っていないと患者さんの安全を守れません。
がん化学療法の薬 はや調べノート
各薬剤毎に、基本情報や時期による注意点、ケアの要点などが見開きのページで短く端的にまとめられています。
- 第1章:分子標的薬(チロシンキナーゼ阻害薬)
- 第2章:分子標的薬(抗体薬)
- 第3章:分子標的薬(mTOR阻害薬)
- 第4章:分子標的薬(プロテアソーム)
- 第5章:分子標的薬(ビタミンA誘導体)
- 第6章:ピリミジン拮抗薬
- 第7章:プリン拮抗薬
- 第8章:葉酸拮抗薬
- 第9章:白金製剤
- 第10章:アルキル化薬
- 第11章:抗生物質
- 第12章:トポイソメラーゼ阻害薬
- 第13章:微小管阻害薬
- 第14章:ホルモン剤
- 第15章:抗癌剤以外でレジメンに入っている治療薬
仕事中、担当患者さんの使用する薬剤の特徴を覚えられていない時、さっと調べるのに役立ちます。