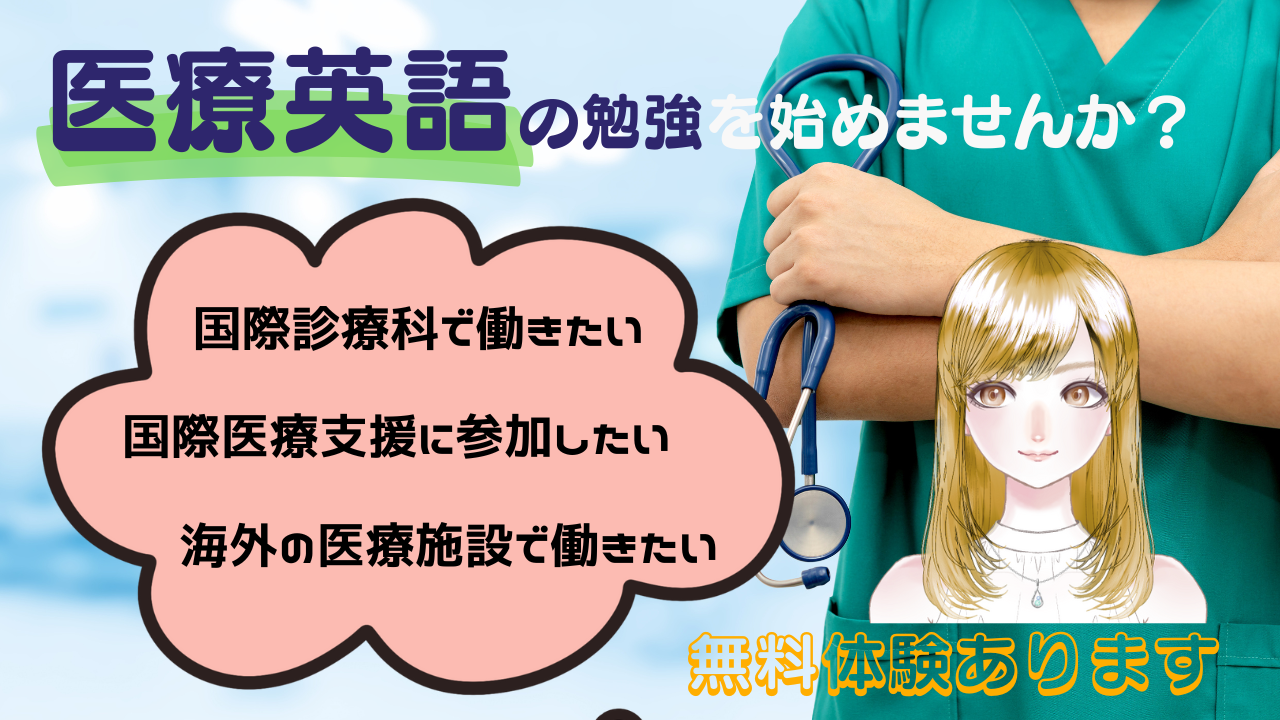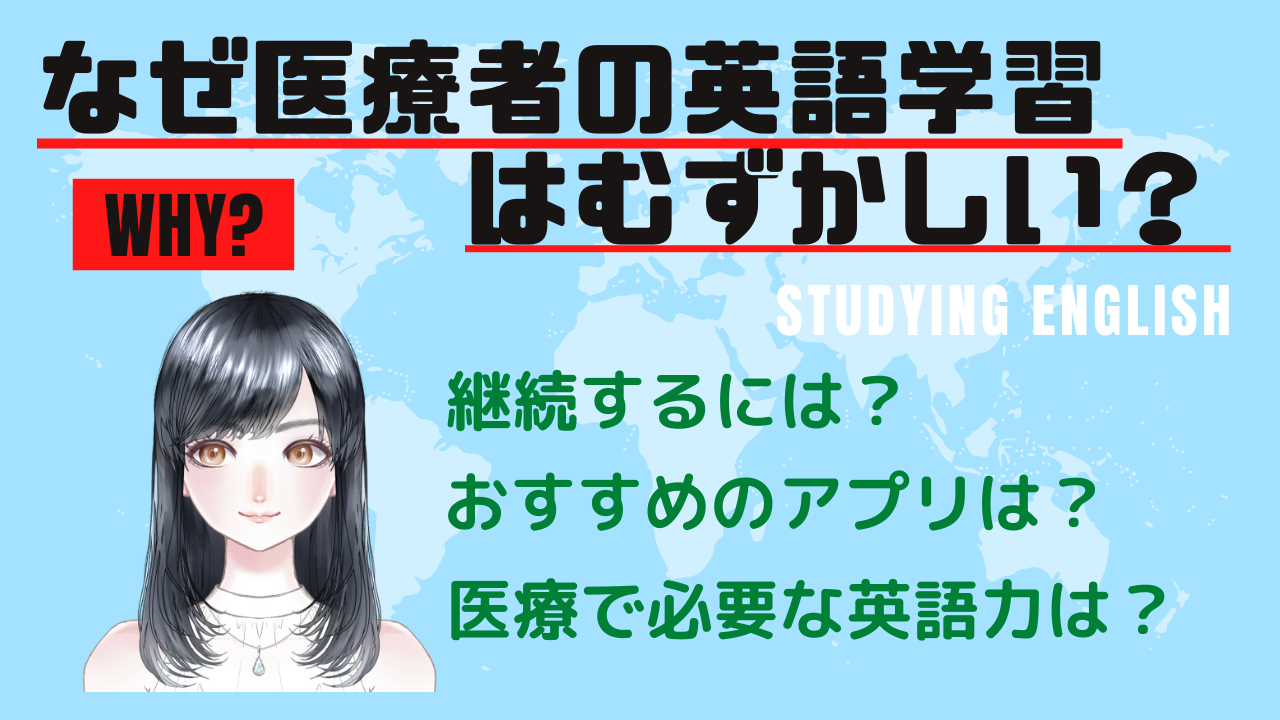英語が好き、英語が得意という医療関係者の皆さま。
日本医学英語検定試験、通称「医英検」をご存知でしょうか?
医療英語に特化した英語検定で、合格すれば達成感を得られ自信になりますし、就職活動や転職活動の際に履歴書へ記入でき、強みとなります。
新型コロナウイルスの状況次第ではありますが、医療従事者は外国人患者さんと関わる場面がありますし、医療用語を英語で理解できると職場で活躍できるかもしれません。
今回2022年6月12日に第15回日本医学英語検定試験を受けてきましたので、その感想や今後受ける方へおすすめの勉強方法などをシェアしたいと思います。
長い記事になりますので、目次を参考に気になる部分だけでも読んでいただけたらと思います。
医師のカルテも、たまに英語ばかりで書く先生いますよね(読むスタッフは全員日本人なのに・・・笑)
こんな人にオススメ
- 医療英語に興味がある
- 日本医学英語検定試験について知りたい
- 医英検の勉強法を知りたい
- 医英検を受けた感想を知りたい
本記事の内容
- 日本医学英語検定試験とは
- おすすめの勉強法
- 試験形式、当日の注意点など
日本医学英語検定試験とは
日本医学英語検定試験(医英検)は、“日本の医療・医学の国際化を普遍的に促進することを目的として、日本医学英語教育学会が主催する医学・医療に特化した英語検定試験”です。
「医学英語」を冠した検定試験は少ないため、医学英語運用能力を客観的に評価できる指標となります。
1年に1回全国で開催されています。(3・4級の試験会場は、2022年は北海道・東京・愛知・滋賀・大阪・岡山・福岡・佐賀)(前回と同様なら、1・2級は東京のみ)
2022年度は、3・4級は6月の第2日曜日、1・2級は2023年1月の予定
必要となる能力
①医学・看護・医療技術の書籍・文献を英文で読む
②医学・看護・医療技術等に関する情報を英語で聞き/話し、伝える
③医学・看護・医療技術等に関する情報を英文で書き、表現する
上記を総合的に評価しますが、受験する等級により、試験内容が異なります。
等級と試験内容、難易度、検定料
基礎級(4級)
基本的な医学英語運用能力を有するレベル
対象者の目安:医科大学や医療系大学在学あるいは卒業程度
筆記試験のみ(90分間、4択のマークシート形式)
検定料:6000円
応用級(3級)
英語で医療に従事できるレベル
対象者の目安:医師・看護師・医療従事者、通訳・翻訳者
筆記試験(90分間、4級と問題は異なる)とリスニング試験(30分間、4択のマークシート形式)
検定料:9000円(※準3級の人がリスニング試験のみ受験する場合は3000円)
※筆記は合格ラインに達していたが、リスニングで合格できなかった人は「準3級」
プロフェッショナル級(2級)
英語での論文執筆・学会発表・討論を行えるレベル
3級合格済+筆記試験(80分間、自由筆記3問)とプレゼンテーション試験(口頭発表10分、質疑応答15分)
検定料:15000円
エキスパート級(1級)
医学英語教育を行えるレベル
対象者の目安:2級受験者を指導できるレベル
2級合格済+面接試験(30分)と医学英語あるいは医学英語教育に関する業績の事前審査
検定料:15000円
※3・4級は、7割以上が合格の目安です。(3級は筆記とリスニングそれぞれ7割以上)
※最新情報は公式サイトより確認してください。
受験対象
資格の制約はないため、医療従事者、教育者、学生、出版などの業界に関わる人、など多種多様です。
しかし、2級・1級を受験する場合は、それぞれ3級、2級に合格済という条件はあります。
私は今回3級を受験してきました。
3級と4級の違いは筆記試験の難易度とリスニング試験の有無だけですが、3・4級と1・2級の間にはかなりの難易度の壁があると思います。
3・4級なら気軽に受験できるのではないでしょうか?
3・4公式テキスト
受験する方は、公式テキストの購入は必須だと思います。
リスニング問題を含め、問題の傾向と対策、練習問題、日頃の勉強法の提案、過去問、過去問の解説、覚えておくべき専門用語一覧の資料など、内容は盛りだくさんです。
どんな試験なのか、どの程度の語彙が必要なのか、文法のレベル、長文読解の文字量など、試験を受けるにあたり必要な情報ばかりです。
英語に関する私のスペック
・小学校:近所の英会話スクールに通う(おばちゃんが個人でやっているレベル)
・中学校:小学校時代に英語を始めていたおかげもあり、テストは安定して9割以上、成績5段階中「5」
・高校:進学校でレベル高かったのもあり落ちこぼれ、テストは安定して5割未満、成績10段階中「3」
・看護学校~社会人:海外旅行が大好きで、観光レベルの英語はなんとか使える
・留学:約4年前オーストラリアへ1年間留学し、語学学校+看護系の学校へ通学、レストランと老人ホームで仕事
・その後:オンラインの英語スクールを始めるが、仕事で予習・復習ができず、中断・終了
外国人患者受け入れ制度のある病院で働くが、コロナの影響で外国人患者さんほとんどなし
という感じです。
学生時代は全然英語が好きではないし苦手でしたが、海外旅行で外国人とコミュニケーションをとる中でだんだん英語が好きになりました。
留学を機に、医療英語に興味を持ちました。
オーストラリアで出会った先生が、「英語を使えるようになったら、インターネットから得られる情報や交流できる人数が日本語だけの時と比べて何百倍にもなります」と言っていたのが印象に残っています。
一気に世界が広がる気持ちでした。
勉強開始時期と勉強方法(失敗談)
正直、今回の試験の手応えはあまりよくなかったので、参考にはなりません(笑)
次の「おすすめの勉強方法」に反省点を踏まえた内容をまとめています。
勉強開始時期
留学を終えてからは、ほとんど英語に触れない生活をしていました。
医英検を知り、公式テキストを購入したのが2021年夏ですが、ほとんど本棚に入れたまま、勉強していませんでした。
2022年4月、仕事の環境が変わり時間に余裕ができたこと、試験まで2か月程度しかないことから、本腰を入れて勉強を始めました。
勉強方法
公式テキストは1冊のみであり、「これさえ完璧に押さえておけば大丈夫でしょう」と高を括っていました。
また、「英語の試験は語彙力で勝負!」と学生時代に聞いたことがあり、単語がわかればほとんど文章は読めると思っていました。
医学英語の語彙は特殊なので、語彙力が重要というのは間違いではありませんが、「知らない単語が出てきたときに推測する力」も必要です。
私はひたすらテキストに載っている英単語を覚える作業ばかりやっており、英文に触れる機会があまりにも少なかったです。テキスト以外には、YouTubeで医療系英単語の聞き流しなど。
リスニングは留学経験を過信し、「語彙がわかれば聞き取れるでしょう」とまたまた高を括り、テキストに載っているリスニング問題のみ、繰り返し聞きました。
おすすめの勉強方法
診療科別(領域別)に単語帳を作成する
公式テキストは実際の問題が複数載っているため、内容はあちこち飛びます。
例えば、1問目は人体の骨の話。2問目はアレルギーの話。3問目は赤ちゃんの話。4問目は抗がん剤治療の話。5問目は大気汚染が人体に及ぼす影響の話、など。4択の選択問題なので、そのページに出てくる骨の名前は4つだけですが、実際に覚える必要のある骨の名前はたくさんあります。
また、テキストの最後には「覚えておくべき専門用語」として約3500の英単語と日本語訳が載っており、大変役立ちます。
しかし、それはアルファベット順に記載されているため、関連する言葉を並べて確認することはできません。
例えば、「aterium 心房」は最初の方に載っており、「ventricle 心室」は最後の方に載っています。
産婦人科の病名も、「abruptio placentae 胎盤早期剥離」と「threatened abortion 切迫流産」など全然違うページに載っています。
また、日本語では同じ意味の言葉でも、英語だと複数の表現方法がある場合、長文読解問題で文章と設問が違う表現をしていると、混乱してしまうことがあります。
例えば、文章中には「peripheral edema(末梢の浮腫)」と書いてあり、設問では「swelling in the extremities(四肢の腫れ)」と書いてあるとします。どちらも「手足の浮腫み」として同じ意味で使われています。このような場合は、edemaとswelling、peripheralとextremitiesを並べて記憶しておくと、問題で言い換えられているときに困らないです。
言い換えられている問題は、非常に多い印象です。同じ言葉だと、問題が簡単になってしまいますしね。また、リスニングは医療者と患者さんの会話場面を聞く問題が多くあり、会話中は簡単な言葉を使い、問題は専門用語になるという場合もあります。
例えば、尿について会話場面では「pee」、設問では「urine」など。
そこで、関連する内容をまとめた単語帳を自作すると、効率的に覚えられるのでおすすめです。
私の場合は、「消化器」「循環器」「呼吸器」「皮膚」・・・「病名」「薬名」「論文で出てくる言葉」など、診療科別+αにまとめ、その中でも<解剖><症状><病名><手術名>など分けてまとめることで、見やすく作成しました。
単語帳アプリは失敗
単語帳アプリを使用すれば、覚えられていない単語だけ反復できるようピックアップする機能や、忘れた頃に再度見せてくれる機能など、いろいろ充実しており便利です。
しかし、私のスマートフォン端末やアプリの使用状況では、3000~4000語の英単語を登録すると重たくなり、動きが悪く画面が変わるのを待つためにかなり時間がかかりました。
何十時間もかけて英単語を登録したのに、全く効率的に勉強できなかったため、ほとんど使っていません。
単語帳作成におすすめはスプレッドシート
そこで、個人的に超超おすすめなのは、Googleのスプレッドシートです。
Excelに似た、文章を表のように書けるアプリですが、便利な点が複数あります。
①いろいろな端末から閲覧、更新できる
Googleアカウントで紐づけしている端末を使用すれば、パソコンからでもスマートフォンからでもスプレッドシートを更新することができます。
例えば、初めて作成する時にはパソコンを使用し一気に書く、続きは気分を変えてカフェでやるのでテキストを見ながらスマートフォンで更新する。帰宅後スマートフォンで動画を観ていたら知らない単語が出てきたため、動画アプリを閉じずにパソコンから追加する、など。そのとき手元にある使いやすい端末で閲覧、更新できるのは、自由自在で本当に便利です。
②内容の追加・修正・整理をしやすい
手書きの単語帳だと、関連した内容を同じページにまとめたいのに増えてしまってページを跨いでしまう時があります。
また、手書きでもアプリでも、例えば産婦人科の内容を産科と婦人科に分けたほうが見やすいと後から気づいた時など、新たにページやフォルダを作って登録し直し、となると手間です。
そこでスプレッドシートなら、コピー&ペーストで簡単に内容の追加・修正・整理ができます。
他にも、勉強開始直後は知らない単語を全部書いたけど、勉強している中で何度も出てきてもう完全に覚えてしまった場合など、削除したり、ほとんど見なくてよい記憶済ページに移動させることもできます。
③画面で見ることもできるし、印刷して持ち運ぶこともできる
出先で少し時間がある時、その隙間時間も暗記に使いたいと思います。
スマートフォンであれば、画面の拡大の程度次第で画面に英語だけ見えるようにしたり、日本語だけ見えるようにしたり、自分の記憶しやすいよう部分的に隠したりできます。
また、スマートフォンを触れない環境の場合や、暗記は画面より紙の方が見やすくて好き!という人は、印刷して持ち運ぶこともできます。
定期的に内容を変更して印刷し直せば、書き込みも気兼ねなくできますし、鞄の中でボロボロになっても構わないですし、使い勝手抜群です。
テキストの資料は辞書のように活用
公式テキストの資料である単語集はアルファベット順に記載されているため、自分で見やすいように関連した内容をまとめた単語帳を作成することをおすすめしましたが、テキストの資料もとても優秀です。
活用方法としては、知らない単語をテキストの資料で調べることです。すると、似たスペルで違う意味を持つ単語がたくさん目に入ってきます。
試験では、似たスペルの単語から選ぶ4択問題もあるので、非常に役立ちます。
例えば、「除細動」を選ぶ問題で、a) defibrination b) defibrillation c) defibrillator d) deficiency という4択の場合があります。
内容としては、a) 脱線維素、c) 除細動器、d) 欠乏症 とバラバラな選択肢ですが、スペルが似ていることで難しくなっています。
こういった問題の対策ができるため、自作の単語帳だけでなく、テキストの資料を使って暗記することも重要です。
YouTubeも活用
テキストやスマートフォン、単語帳を使った勉強に疲れてしまったときは、YouTubeでの勉強もおすすめです。
病名や症状などを、英語と日本語を交互に表示し発音してくれる動画は、発音を覚えるために役立ちます。
スペルと意味だけ覚えていても、発音を勘違いしているとリスニングの際に致命的ですし、試験対策ではなく実際の使用場面で伝わらないという大問題も生じます。
私の通っているジムのランニングマシンはYouTubeを観ることができるため、走りながら英単語を聞き流していました。
また、リスニング対策としてもYouTubeは非常に便利です。
英単語だけでなく、病院を想定した会話集などもあります。
さらに、YouTubeの強みは再生速度を調整できることです。
慣れないうちは通常の速度だと早くて聞き取れないことも多いため(特に英語学習向けではない通常の会話の動画など)、自分に適した再生速度を選べるのは大きなメリットです。
テキストに紹介されている日々の勉強法を実践
公式テキストの良いところの1つは、この試験を受ける人に適した勉強法を紹介してくれていることです。
例えば、医療に関連した文章をインターネット上で読むために、WHO(世界保健機関)やFDA(アメリカ食品医薬品局)など多数の信頼できるサイトをURLと共に紹介してくれています。
これらを日々少しずつでも読んでいると、頻出単語の記憶定着や、医療場面での独特の言い回しなどが身に着きます。
また、リスニング対策を兼ねる場合は、アメリカのABC、CNN、PBC、イギリスのBBCなどの海外マスコミのサイトが有益であると紹介されています。
私は油断しており、テキストで紹介されているサイトで勉強することはなかったですが、試験対策だけでなく本当の医療英語力を身につけるためにも、紹介されている勉強法を毎日コツコツ継続することが大切だと思います。
当日の感想
全体を把握する
例年筆記試験は90分間で、問題数は多少前後するようですが、約60問です。
今回は全部で59問あり、(問題用紙は回収されるため記憶が曖昧ですが)前半は、語彙、プラティカル問題(写真やグラフを参照する問題)、会話読解で計35問あり、後半が24問の長文読解だったと思います。(長文読解は5つの文章があり、設問が各4~5問で計24問)
私は試験というものを数年間受けていなかったため、基本である「試験の全体を把握する」ということを忘れ、1問目から順に解いていきました。
そして、後半の長文読解で絶望しました(笑)
公式テキストは3・4級が載っているため、4級の問題も見ていたからか、長文読解の文章量が思っていたより非常に多く感じたのです。(5つとも文章量の差はほとんどなく、ページの半分以上が文章、そのあと設問)
また、設問がページを跨ぐこともありますが、文章量の件で動揺しており気づきませんでした。設問2つを頭に入れ、文章を読み始め、大きな問題1つ終わったと思ってページをめくると設問がさらに3つ追加で出てきました。読み直しです。設問の内容を把握してから文章を読みたかったのに・・・
慌てていると、こんなうっかりも起こります(笑)
私の教訓は、後半や終盤に焦らないために、開始直後にそれぞれの問題が大体何問ずつあり、トータルどれくらいの問題量なのかを把握することが重要ということです。
時間配分に注意
これも試験慣れしていないことによる失敗ですが、時間配分を考えていませんでした。
公式テキストでは、3級・4級それぞれ1回分ずつ過去問題等で構成された実際の試験を模した問題が載っています。
なので、実際の試験を想定した時間を測って行うような練習は、1回しかできません。
過去に医英検を受けた人の感想をネット上で読んでいると、「時間には余裕がある」「30分程度見直しに充てた」など書いている人が多く、私は全く時間配分を考えず、前半のんびり時間をかけて解いていました。
そこで、時間が半分以上経過しているのに、先ほど記載した想定以上の長文です。
どちらかというと語彙より長文読解が得意と思っていたのに、長文読解にかけられる時間が非常に短く、大慌てで読むことになり、時間を気にしているため集中力もなく、散々でした。(T_T)
先ほど記載した全体の把握に加え、把握した量をどんな時間配分でやっていくか、最初に考えることが重要です。
例えば、長文読解の文章量が思っていたより長かったため、試験時間の90分中50分を長文読解に使おう。などです。
そうすると、前半の問題もさほどゆっくりできないことに気づけるはずです。
※ちなみに私は学生時代から英文を読むスピードが遅い方で、TOEICが時間内に終わらないレベルです。
医療英語の語彙は、接頭語や接尾語から意味を推測できるのが特徴ですが、正直推測している時間はないので、考えなくてもすぐに思い出せるよう暗記しておくと良いと思います。
接頭語、接尾語とは、
例えば「arteriosclerosis (動脈硬化症)」の場合、接頭語のarteriで動脈、接尾語のosisで症(異常な状態)がわかり、真ん中のsclerに硬化の意味があることから、「動脈が硬くなる病気のことだな」と考えられます。
試験当日、時間が全然足りなくなってしまった私は、長文読解を丁寧に読んで確実に点数を取りいくつかの問題を諦めるか、全体に軽く読んで正答率は低くなるが全部の問題と向き合うか、迷いました。究極の選択(笑)
リスニングについて
リスニング試験は30分間で全15問でした。(記憶が曖昧ですが、)ダイアログ(医師と患者の会話形式)が7つ、ケースプレゼンテーション(医師が患者症例を発表する形式)が3つで、それぞれ1~2問の設問があり、合計15問でした。
ダイアログとケースプレゼンテーション、設問はそれぞれ2回繰り返されますが、a~dの選択肢は読まれません。選択肢に目を通すための時間が数秒ありますが、そこで知らない単語を推測したり思い出そうとしたりすると時間が足りなくなってしまうため、リスニングでも語彙力は重要だと感じました。
傾向としては、ダイアログの方が専門用語が少なく一般的な言い回しが多く、ケースプレゼンテーションは専門用語が多いです。
どちらも読まれるスピードは同じ程度に感じました。速すぎることはないです。
ちなみに、テキストに載っているのと同じ内容の例題が本番もありましたが、例題は試験時間の開始前に行います。
読むスピードが遅い私は、「例題の放送中に問題文や選択肢を読み始めようかな」と考えていましたが、それは不可能です。
例題のときは例題のページしか見ることができません。
そして、リスニング試験の30分間はかなりぎりぎりまでリスニングの放送を聞くことになるため、「問題用紙に回答をメモして最後にまとめて塗ろう」という作戦はできません。
1~3問程度、どうしても迷う問題だけ塗らずに、最後ぎりぎりで考えることはできると思いますが、焦ること間違いなしです(笑)
私は迷う問題があると、次の問題が始まっても前の問題を気にしてしまい集中力が欠けるので、潔く諦めることが必要だと思いました(笑)
試験当日の持ち物について
必要なもの(机に置けるもの)は、受験票、HBまたはBの鉛筆、消しゴム、鉛筆削り、時計のみです。
受験票は郵送されたものに自分で写真を貼付しておく必要があるため、余裕を持って数日前に準備することをおすすめします。
鉛筆については、鉛筆削りも机に出しておくことができますが、鉛筆を複数本用意して削らなくていい状態にするほうが安心できると思います。
時計については、時計以外の機能がついている時計は禁止です(Apple Watchなど)。私が参加した会場は部屋に時計があり、どの席からも見えるようにはなっていましたが、会場によっては見えづらい可能性もあるので、用意するほうが安心です。
その他、3級を受ける方は、筆記試験90分とリスニング試験30分の間に休憩があるため、必要に応じて飲食物も持っていくと良いかもしれません。
水分と、集中力をあげるためにチョコレートなど、好みに合わせて用意しましょう。(私が参加した会場は飲食の制限はありませんでしたが、もしかしたら会場によっては制限があるかもしれません)
今後の目標
今回の試験の結果は、8月末までに郵送でお知らせがあるそうです。
結果が良くても、2級は一気に難しくなるため、2級への挑戦は当面しないつもりです。
結果が良くなかった場合は、来年も3級をリベンジしたいと思います。(4級に下げない)
結果がどちらであれ、まだまだ知らない言葉はたくさんあり、時間の余裕もなかったので、勉強は継続しようと思います。
今回約2か月で試験に臨みましたが、短期間での準備にはやはり限界があると感じました。
語彙についてはなんとかある程度は詰め込めますが、長文の読むスピードを速くすることや、リスニングで正確に聞き取ることは、日々の勉強の積み重ねが重要だと思うので、公式テキストで紹介されていたサイトなど利用して毎日コツコツと英語に触れていこうと思います。
CBMS(国際医療英語認定試験)
今度は、11月にあるCBMSを受けることを検討中です。
医英検は年に1回のため、来年再度受けるにしても受けないにしても、今後も医療英語へのモチベーションが下がらないように他にも目標があると良いと思ったからです。
ちなみにCBMSはTOEICなどと同様、合否の判定ではなく、点数での評価のみです。
今の自分の力を知るため、前年よりどれくらい成長したかを知るために、有用な試験です。