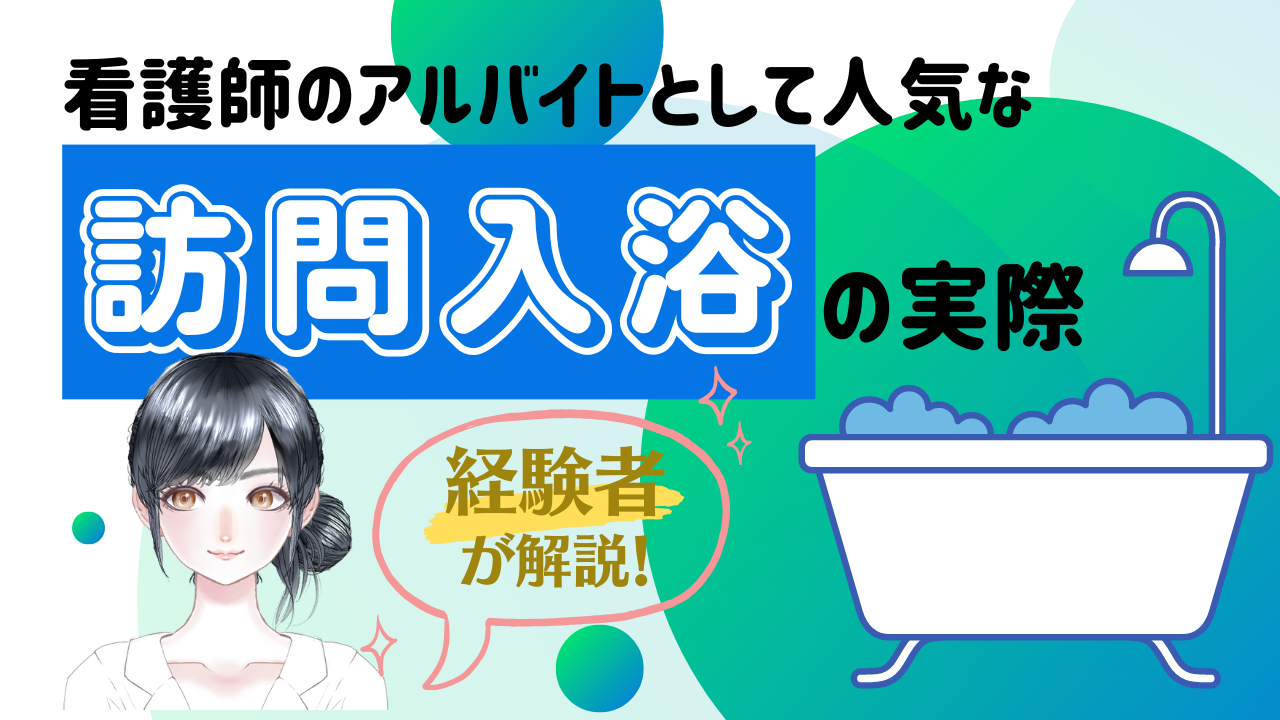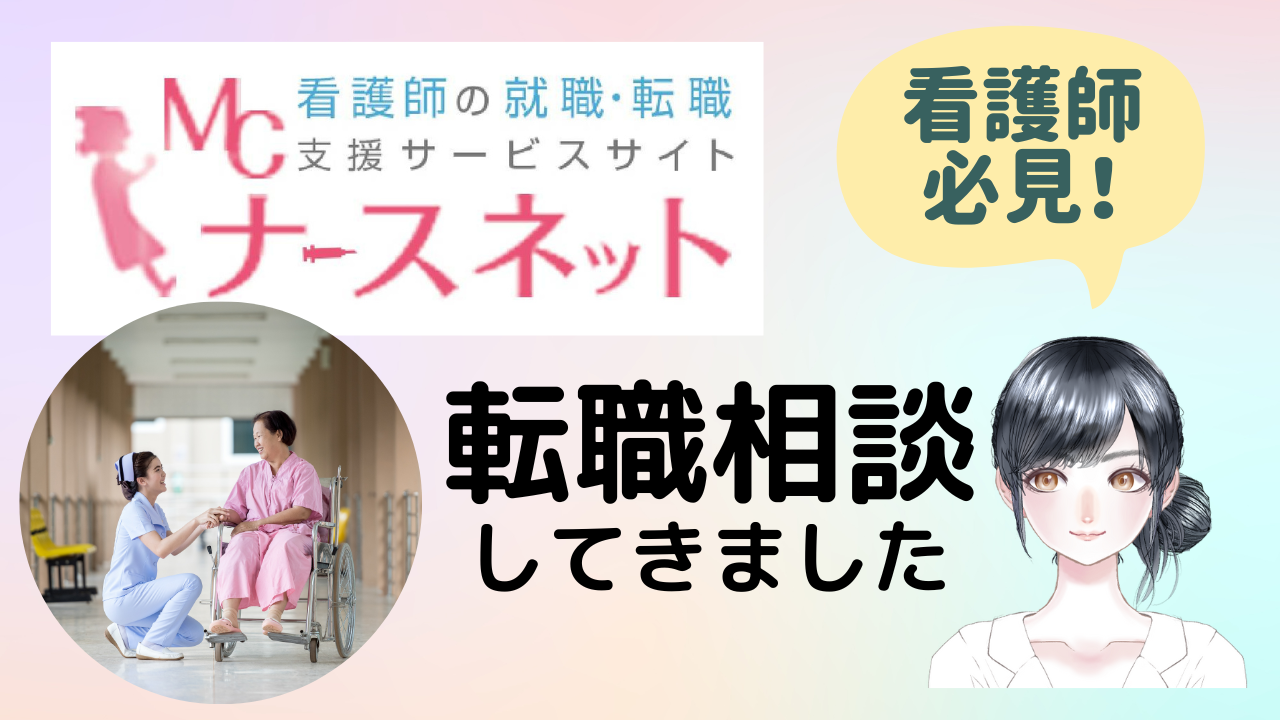看護師が働ける場所は、病院(病棟・外来)、施設(老人ホーム、デイサービス、ショートステイなど)、クリニック、訪問看護、保育園など、さまざまです。
また、看護師には高時給のアルバイトもあります。
健康診断の採血、コロナのワクチン、コロナのコールセンター、訪問入浴などです。
看護師は転職をする際、貯金をしていた方はすぐに再就職せず、失業手当をもらいながらのんびりと次の仕事を探す方も多いと思います。
また、留学や引っ越しなどを控え、まとまったお金を貯めるために高時給の仕事を複数行う方もいると思います。
しかし、派遣法の改定などもあり、失業手当をもらいながらどんな単発アルバイトでもできるわけではありません。
失業手当を受給中の場合、週に20時間以上の労働や30日を超える雇用契約は結べないためです。
しかし、看護師のアルバイトでイメージするものの多くは、30日以上の契約がないとできないものばかりです。
その中の例外が、訪問入浴なのです。
訪問入浴は単発のアルバイトとしても人気ですし、もちろん事業所に正社員として入職することもできます。
病棟や施設の経験だけの方は、「訪問入浴」という言葉は聞いたことがあっても実際の仕組みや仕事内容をイメージできない方も多いと思います。
この記事では、訪問入浴を経験したことのある私が、訪問入浴の流れ、看護師の役割、訪問入浴のやりがい等を紹介します。
こんな人にオススメ
- 看護師のアルバイトを始めたい
- 訪問入浴に興味がある
- 身近な人が、訪問入浴の利用を検討している
本記事の内容
- 訪問入浴とは?
- 訪問入浴の流れ
- 訪問入浴での看護師の役割
- 時給、疲労度、やりがい
- 向かない人
- おまけ:あると便利な持ち物
訪問入浴とは?
訪問入浴は、介護保険で利用できるサービスで、自立して入浴ができない、家族の介助のみでは入浴ができない在宅で過ごしている方を訪問し、特別な浴槽を自宅へ運び込み入浴を介助するサービスです。
基本的には、要介護1~5の介護認定があり、医師から入浴許可を得ている人が対象となります。
訪問介護での入浴サービスは1人介助で入浴できる方を主な対象としているのに対し、訪問入浴は3名程度のスタッフで訪問するため、全介助の寝たきりの方でも利用できます。
介護保険を利用できるため訪問入浴の自己負担額は1割で、1回当たり1000~1200円程度のことが多いです。
週1~2回利用される方が多いです。
訪問入浴の流れ
出勤
訪問入浴サービスを提供している事業所に出勤し、その事業所のルールに基づき朝礼に参加します。
その日のチーム分け(看護師1名+介護士2名の3名チームであることが多い)と、利用者の訪問時刻の確認を行います。
病棟看護師でいう、「部屋割り」「受け持ちの割り振り」「チーム(ペア)決め」のようなものですね。
物品の準備
看護師が準備するのは、
- カルテ(紙カルテorタブレット)
- 体温計、血圧計、パルスオキシメーター
- 手袋
- 手指消毒液
- ハンドソープ、ペーパータオル
- ゴミ袋
- 筆記用具
- ドライヤー
- ガーゼ、テープ、はさみ
- ドレッシング剤、絆創膏
- 綿球、綿棒
などです。各事業所のマニュアルに沿った準備物品があります。
介護士のスタッフ2名は、
オペレーターと呼ばれる運転手(兼リーダー)と、看護師と共にケアを行う介護スタッフに分かれます。
それぞれマニュアルに沿って持ち物を確認します。
- 浴槽やホース
- 消毒液
- 防水マット
- タオル類
- 洗面器やボディーソープなど
- 連絡用の携帯電話(スマートフォン)
訪問
1時間に1件の訪問であることが多いです。9時~17時で、1時間休憩を含むため、1日7~8件の訪問です。(事業所によっては17時以降も実施している場合があります。)
1人あたり40~50分で準備→入浴→片付けの全てを終え、次の訪問先に車で移動します。
挨拶
訪問の際には、元気よく利用者さんとご家族へ挨拶をします。
単発のアルバイトの場合、「はじめまして、看護師の○○と申します」と挨拶をしますが、訪問入浴自体が初めてであることを伝えると不安に感じさせてしまうため、敢えて伝える必要はありません。
訪問入浴の利用者は、状態が安定しており入浴許可が出ているため、基本的には明るい態度で訪問したら良いです。(訪問看護の場合、状態が悪化している時など、いつでも元気に訪問することが望ましいとは限りません)
手洗い
「手洗い場をお借りします」と伝え、事業所から持参したハンドソープとペーパータオルを使用し手洗いを行います。
お借りできない場合は、持参の手指消毒を使用します。
自宅のハンドソープやタオルを借りたり、ペーパータオルのゴミを残してきたりしてはいけません。(ペーパータオルはゴミ袋に入れ、事業所へ持ち帰る)
バイタルサイン測定
体温、血圧、脈拍、呼吸数、SpO2を測定し、カルテに記録します。
利用者さんの手持ちの記録用紙がある場合が多いため、有無を確認し、その用紙にも記録します。
カルテでこれまでのバイタルサインの推移を確認し、利用者さんの症状の変化や訴えも確認した上で、入浴できるかどうかを判断します。
看護師がバイタルサイン測定をしている間に、介護士の2人が床に防水マットを敷き、浴槽とシャワーを準備し、配水の調整をしてくれます。
カルテには患者さんの希望の湯の温度が記載してあり、希望に合わせた温度で調整します。
脱衣
利用者さんへ声をかけながら、脱衣を行います。
羞恥心に配慮し、乾いたタオルで体を隠します。
入浴(洗髪・洗体)
ベッドや車椅子から浴槽へ、利用者さんを移乗します。
利用者さんの体型や介助量に応じて、2~3名のスタッフで抱きかかえたり、移乗用のシートを利用したりします。
浴槽に入ったら、介護スタッフと分担しながら洗顔・洗髪・洗体を行います。
使用する洗顔料やシャンプー、ボディーソープは利用者さんの希望に合わせます。
事業所ごとのルールがあります。シャンプーを流す際には目や耳に湯が入らないよう2名で対策をする、陰部を洗うのは同性のスタッフが行う、など慣れたスタッフに確認しながら実施すると良いです。
看護師と介護士の2名で入浴介助をしている間に、希望があればもう1人の介護士がシーツ交換を行います。
カラーリング剤を配合したトリートメントを使用する方もおり、その場合は使用方法を確認し、「5分以上置く」などの注意事項を守って手順を工夫します。
上がり湯
洗い場はなく浴槽の中で洗体するため、上がり湯は必須です。(浴槽部分と洗髪台部分に分かれているため、シャンプーの排水はできます。)
利用者さんは浴槽に直接入っているのではなく、1枚シートに乗った状態で入浴しているため、シート部分のみを上昇させることで、浴槽から上がった状態でシャワーの湯を浴びることができます。
寒さ対策が重要となるので、上がり湯をかけたらすぐに乾いたタオルで拭いていきます。
軟膏の塗布
カルテを確認しながら、利用者ごとに必要な軟膏類を塗布していきます。
ご家族からの情報で、往診医の指示で軟膏の変更がある場合などは、カルテにその旨を記載します。
着衣
ご家族が用意している新しい衣服を着るため介助します。
必要に応じてドライヤーも行います。
看護師と介護士1名で軟膏塗布や着衣を行っている間、もう1名の介護士は浴槽の消毒や片付けを行います。
バイタルサイン測定
入浴後の体調変化の確認としてバイタルサイン測定を行い、記録します。
手洗い
再度手洗い場をお借りし、手洗いを行います。
記録
訪問中に記録が終わらない場合は、車での移動中に記録を行います。
また、移動中に次の訪問者の情報収集も行います。
退勤
その日の予定の訪問入浴が全て終了したら、事業所へ戻ります。
使用した物品の清掃や補充を、事業所ごとのチェックリストに沿って行います。
ユニフォームの洗濯等も事業所内でスタッフが行う場合もあるため、事業所のルールに従い片付けや翌日の準備をして、退勤します。
訪問入浴での看護師の役割
入浴の可否の判断
バイタルサインや症状の変化を観察し、予定通りに入浴が可能か判断します。
入浴が難しいと判断した場合は、部分浴や清拭に変更することもあります。
また、状態が著明に変化している場合は、ご家族に訪問看護師へ連絡するよう助言する場合もあります。
入浴介助、状態の観察
入浴中は、看護師は介護士1名と共に常に利用者さんの状態を観察しながら介助します。
軟膏塗布
軟膏の使用やガーゼを当てる等の処置は、看護師の責任で実施します。
気切部のガーゼ交換は医療行為に当たると判断する場合もあるため、事業所のルールに従い、必要に応じてご家族へ実施を依頼します。
入浴後の状態変化の有無を観察
入浴を終え、ベッドや車椅子へ戻った後に、バイタルサインや症状の変化の観察を行い、異常がないことを確認します。
異常があれば、ご家族に訪問看護師へ連絡するよう助言する場合もあります。
記録
入浴前後のバイタルサインや利用者の状態、皮膚トラブルの有無や皮膚に処置を行った内容、湯の温度、シーツ交換を実施したか等、事業所で決められた記録用紙に沿って記録を行います。
利用者さんから、摘便や吸引などの希望があっても、訪問入浴の看護師は入浴に関することしかできません。
原則、医療行為は行いません。
時給、疲労度
時給の相場
事業所や派遣会社、または地域によっても相場は変わりますが、
派遣の看護師の時給は1700円~2500円程度が多い印象です。
移動時間も時給は発生するため、実際の稼働時間を考えると看護師のアルバイトの中でも高時給であると思います。
例えば、9時からの訪問が40分で終了し、次の訪問が10時の場合、近くのコンビニの駐車場などで時間調整のための休憩があります。
疲労度
訪問入浴は重労働、というイメージがありますが、個人的には想像していたほどの疲労感はなかったです。
病棟でのケア当番の場合、もっと多くの人数を次々に入浴介助するので、それと比較すれば移動時間や時間調整の待ち時間があり、ゆったりしています。
しかし、自宅に訪問するため、療養場所が2階の場合は浴槽などたくさんの物品を階段で運ばないといけないため、きついです。
また、ベッドから浴槽までの移動は、自宅のスペースによっては横並びに設置できないため、2~3名のスタッフで患者さんを抱えて移動することになるため、利用者の体格によっては重労働です。
事業所によって男性スタッフが少ない場合、女性スタッフだけでの介助となり、体力的にきつい場合もあります。
男性スタッフがチームにいてくれると、頼もしいです。
個人的には、実際の働いている時間や仕事内容を考えると、お得な仕事だと思います!
訪問入浴がおすすめの理由
メリット
- 利用者さんの笑顔を見れるため、やりがいがある
- 3人組で行動するため心強い、安心感がある
- 想定外の残業はほとんどない
やりがいがある
日本人は、入浴が大好きな人が多いです。
訪問入浴を楽しみに1週間待ってくれており、「気持ちいい、ありがとう」と笑顔で言ってくれる方が多いです。
利用者さんの笑顔やお礼の言葉をもらえることは、何よりのやりがいであり、モチベーションとなります。
チームで対応できる
訪問看護は1人での訪問のため、利用者さんに何か大きな変化があったとき、1人で対応しなければなりません。
また、移動中も1人で、訪問時間以外は孤独です。
しかし、訪問入浴は3人チームであるため、訪問時に利用者さんの様子がおかしい場合、「訪問看護師に連絡しよう」「訪問看護師から往診医に連絡してもらおう」といった相談をしたり、ご家族に状況を説明したり、事業所に中止の旨を報告したりと、手分けしたり相談したりしながら対応できます。
看護師は1人ですが、介護士も経験が長い方は利用者さんやご家族のことを良く知っており、チームで協力できるためプレッシャーは軽くなります。
また、訪問看護は1人で訪問するため、稀にセクハラを受けたり、清掃が行き届いておらず不快な気持ちになることもありますが、チームで訪問するためセクハラを受けることはまずありませんし、不快な気持ちになってもチームで同じ経験をしており思いを共有できます。
家族が在宅していることが多い
訪問入浴の訪問時間は事前に決まっておりご家族へお知らせ済みのため、必要な着替えやシーツ、軟膏類を用意して待ってくれています。
患者さんの状態に何か変化があった時には、その場にご家族がいるため、訪問看護師や往診医などの連絡先がすぐにわかりますし、他の家族を呼ぶ必要があれば対応してもらえます。
また、「ありがとう」と飲み物やお菓子などの差し入れをいただけることも多いです!(本当はもらってはいけないかもしれませんが、関係性があるのでもらってしまいます)
急な残業が少ない
利用者さんの訪問時間が決まっており、基本的には時間を守れないような無理なタイムスケジュールにはなっていません。
利用者さんの状態変化や転倒・転落などの事故が起こった場合は例外ですが、原則余裕のあるタイムスケジュールを組んでいるため、残業はあまりないです。
17時からの訪問があるときなど、事前に残業が確定している日もあります。
訪問入浴が向かない人
デメリット
- 家族(介護者)のやり方やペースに合わせる必要がある
- 移乗など腰痛を招くような重労働がある
- 医療行為はできない
- 車での移動時間が多く、車内で記録をするため酔いやすい
独自のルールを受け入れがたい
ご家族が主な介護者であり、独特のルールを持っている方が多いです。
ガーゼ保護の方法や、保湿剤を塗る範囲、衣服の着脱の手順など、正直「意味があるのかな?」「効率が悪いのでは?」と医療者目線で思うようなことがあっても、身体に悪影響がないことなら、毎日介護している方のやり方や希望に合わせるようにします。
また、自宅の家具の配置などもそれぞれの家庭ごとの決まりがあるため、余程の理由がなければ「狭いので家具の配置を変えてほしい」などは言うべきではありません。
理にかなった看護をしたい、効率的に働きたい、結果が同じなら私のやり方でやらせてほしい、と考えるタイプの看護師は、訪問入浴には向かないかもしれません。
移乗など重労働がある
ベッドから浴槽への移乗は、スタッフ3人で利用者さんを抱えての移動が多いです。(シートなど道具は使用します)
男性スタッフを含むチームの場合が多く、男性スタッフがメインで支えてくれますが、ほとんどの利用者さんは介護度が高いため全介助です。
大柄の利用者さんの場合や、お部屋の広さや造りの兼ね合いでベッドから浴槽までの距離が遠い場合には、汗を流しながら必死で移乗することになります。
また、更衣にも体力を要しますし、道具を車から家の中へ運んだりセッティングしたりするのも重労働です。
午前中は調子よくできますが、夕方の訪問になると正直へとへとです。
医療行為をしたい
訪問入浴では、入浴に関することしかできません。
痛み止めの相談を受けたり、点滴の調整や、摘便・吸引の希望などがあっても、看護師ですが医療行為はできません。
「訪問看護師さんに相談してください」「訪問看護師さんへお願いしてください」としか言えないため、医療行為ができないもどかしさが辛い人には、訪問入浴は向かないかもしれません。
車酔いしやすい
1時間毎に利用者さんの訪問をするため、車での移動時間が多いです。
また、移動中に情報収集をしたり、記録をしたりすることも多々あります。
車酔いしやすい方は、向かないと思います。
あると便利な持ち物
訪問入浴に最低限必要な物品は事業所のマニュアルに沿って準備しますが、個人的に持って来れば良かったな!と思ったものを紹介します。
- ポケットに入るハンカチ
- 替えの靴下
- パーカーなどの上着
- 多めの飲み物
1.ポケットに入るハンカチ
利用者さんの家に訪問すると、室内の温度はさまざまです。
夏場はクーラーをつけて涼しくしている家もあれば、扇風機のみの家もあります。
利用者さんやその夫・妻は高齢であることが多く、私たちより部屋を涼しくはしないことも多いです。
そんな中で希望に応じて熱めのお湯で入浴介助をするとなると、介助者である私たちは汗が止まりません!
前かがみになると利用者さんに汗が垂れそうになりますし、利用者さんの記録用紙やノートにも汗が垂れそうになることがあります。
入浴介助に使うタオルで自分の汗を拭くわけにはいかないので、ユニフォームのポケットに入るサイズの汗拭きタオルは必須です!
2.替えの靴下
利用者さんの自宅を濡らさないように、浴槽の下には大きな防水マットを敷きます。
それを片づける際に、雑巾でマットの水を拭き取るのですが、たまにマットの上の水たまりを思い切り踏んでしまうことがあります。
自分の足が濡れたままだと不快なのはもちろんですが、その後も次の利用者さんへの訪問があるため、濡れた靴下で訪問するわけにはいきません。
濡れてしまったときのために、予備の靴下があると安心です!
3.パーカーなどの上着
訪問の時間調整で、コンビニの駐車場などで休憩する場合があります。
昼食も、事業所に戻る時間がない(または戻ると遠回り、動線が長くなる)場合、コンビニの駐車場で昼食を摂ることがあります。
コンビニを利用する場合は事業所のユニフォームの上からパーカーなどの上着を羽織っておくと、気兼ねなく入れます。
昼食は持参するからコンビニに入るつもりがない、という方も、お手洗いを利用するためにコンビニを利用する可能性があります。
事業所名がばっちり載ったユニフォームでコンビニを利用するのはちょっと・・・となるので、上着を用意しましょう。
また、昼休憩をコンビニの駐車場(車内)で過ごす場合、思いのほか日差しが強く日焼けしてしまうこともありますし、男性スタッフと同乗していると車内のクーラーが結構きついこともあります。
日焼け対策やクーラー対策としても、薄手の上着があると便利です。
4.多めの飲み物
入浴介助を連続でやっていると喉が渇きます。
移動中の時間調整で休憩できる時間があるため、飲水できる機会も多く、思いのほか水分を摂ると思います。
自分1人のためにコンビニへ行ってもらい追加の飲み物を買うのは申し訳ない気持ちになるため、多めに持っていきましょう!
まとめ
訪問入浴は、失業手当を受給中でもできる単発のアルバイトとして人気です。
また、3名チームで行うサービスで、医療行為は行わないことから、看護師の経験年数が少ない人も、比較的安心してチャレンジできる仕事内容だと思います。
利用者さんの笑顔を見られる嬉しさもあるので、重労働ではありますが、個人的にはおすすめの仕事です。
ただ、正社員として働く場合には、日々変化が少なく刺激が少ない仕事であるように感じる方もいると思います。
また、医療行為ができないことで、やりがいが少なく感じることもあるかもしれません。
そして丸1日固定のチームで行動するため、人間関係が問題となる職場もあるかもしれません。
訪問入浴の単発アルバイトをするなら
私は、ここで登録して訪問入浴の仕事を紹介してもらいました。